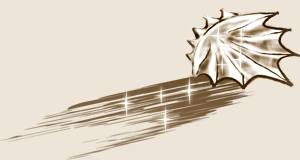聖域の探索者 10.志願の理由
「遺跡探索隊は昨年の秋、事前の予告もなしに、身分を問わずかき集められました。その構成員には、騎士団出身の者だけでなく、傭兵や剣闘士上がり、あまつさえクローネの民まで、さまざまな者たちが含まれています。そんな寄せ集めの集団が組織として機能しているのは、マーカスさんがそれぞれを結ぶ、くさびとなっているからなんです」
「人間たちだけでなく、クローネの民もまとめているとは、たいした人物なのだな」
主は素直に賞賛を述べた。それもそのはず、つい最近まで、人間とクローネは攻める側と攻められる側の立場に別れて争っていたのだ。争いは、双方に決して少なくない犠牲者を生んだ。当然、その軋轢は数ヶ月程度の月日で解消されるようなものではない。きっとこの関係は数代先の子孫の時代まで変わることはないだろう。そうであるにも関わらず、この時期に人間とクローネが一つの組織内に収まっているというのだから、驚くべきことである。
「マーカスさんは、もともと青鷹騎士団の中でも次期団長候補として目されていた実力の持ち主でした。昨年行われた騎士の剣闘試合でも優勝を収めて、その評価を確固たるものとしていました。――でも、あの人はそういったことを鼻に掛けることもなく、身分や肩書きにとらわれず、誰にでも親身になって接してくれるんです。どこか、子供っぽいところもあって、一度甲冑を脱いでしまえば、ぜんぜん騎士らしくないんですけどね」
子供っぽいマーカスの姿が思い浮かんだのか、一瞬、青年の顔が緩んだ。
「結成当初の遺跡探索隊は、それはもう、毎日いさかいが絶えなくて……。特に規律を持たない傭兵たちとクローネたちとの衝突は日常茶飯事でした。それを、毎回のように間に入って諌めていたのはマーカスさんでした。でも、その諌め方というのが、ちょっと変わっていて――ただ止めるんじゃなくて、自分の立会いの下で当事者たちに素手で殴り合いをさせるんですよ。お互い中途半端で終わらせるのは良くないからって……。ところが、いざ勝敗が決まりそうになると、今度は自分が割って入って、負けそうなほうに加担するんです。『喧嘩は許すが、一方的な暴力は許さない』とか何とか言って。それで形勢が逆転すると、今度はまた反対側に加担して……」そう言って、青年は呆れたように笑ってみせた。
「意味がわからないですよね。それじゃ、いつまでたっても決着がつかないんですから。で、当事者たちもそのうちマーカスさんを相手に回して、共闘して殴りかかっていったり……。まあ、それでも、これまでマーカスさんが喧嘩に負けたことなんてないんですけど……」
世の中には変わった人物も居たものだ。マーカスという男は、よほど他人と関わるのが好きだとみえる。それも、言葉で理屈を並べるよりも、身体を使って体現することを優先させるようだ。確かに、寄せ集めの荒くれどもをまとめるためには、そのほうが有効なのかもしれないが……。話を聞くだけでも、なんとも汗臭そうな男の姿が思い浮かんだ。主とは正反対のタイプだ。
「そんなことを繰り返しているうちに、皆いつの間にかお互いのことがなんとなくわかるようになっていって……。そうやって、遺跡探索隊は徐々に組織としての体を成していきました。もちろん、そんなマーカスさんを煙たがって、反感を持つ者も居ます。でも、そんな人たちも、あの人に無関心では居られません。良いも悪いも、みんなひっくるめて、今の遺跡探索隊はマーカスという人物がくさびとなって一つにまとまっているんです」
いつしか青年の言葉は熱を帯びていた。言葉に合わせて身振り手振りが加わっていた。彼の抱く、マーカスに対する尊敬と憧れの念がそこに溢れていた。もしかすると、彼の騎士マーカスに対する信仰心は、女神クローディアへのそれよりも勝っているのではないだろうか?
一気にまくし立てた青年は、そこまで言うと足元に目を落とした。
「本当に、あの人はしつこくて、暑苦しくて、鬱陶しくて……。一度こうと決めたら、何が何でもそれを貫こうとして……。少しは俺の言うことを聞いてくれたって良いのに……」
青年の活き活きとしていた声は一転、どんどん弱く、低くなり、先ほどまでの勢いは鳴りを潜めてしまった。そして、青年の拳が堅く握りこまれた。肩が小刻みに震えている。
――突然、彼はあらん限りの声を張り上げて叫んだ。
「何が『俺に不可能なことはない』ですかッ! 何が『大願成就を果たすまで俺は死なない』ですかッ! いくら足掻いても、無理なことは無理なんですよッ!」
石造りの部屋の中に悲鳴にも似た声が反響した。その鼓膜を破らんばかりの声量に、心臓が飛び出るかと思ったほどだ。
うつむく青年の足元に、大粒の水滴がひとつ、ふたつと落ちて弾けた。
「おい……」
主は明らかに戸惑いの表情を浮かべていた。何せ、他人を慰めるなどといったこととは縁遠い人だ。突如として哀哭する青年を前にして、どうしてよいかわからず、青年に向けて伸ばした手も中途半端なところで止まってしまっている。
私と主は、まるで時間停止の魔法を掛けられたかのように、微動だにできなかった。部屋の空気が再度動きだすためには、青年の感情が収まりをみせるのを待つほかなかった。城の外からは、依然として雑踏の音が聞こえてきたが、張り詰めた空気の部屋の中では、まるで別の世界のことのように感じられた。
やがて――とは言っても、実際にはさほど時間は経過していなかったのだろうが、青年は袖口で目元を拭うと、小さく言葉を漏らした。
「俺は……あの人を置き去りにして、こんなところまで……逃げてきてしまいました……」
騎士マーカスより太陽の宝玉を託されて、遺跡から生還した従騎士。私と主がクランジェルを訪れ、太陽の宝玉の複製品を作ることになる切っ掛けを作った人物――それが彼だった。
従騎士の立場にある者が、この非常時に非番をあてがわれて街の案内役を務めたことで、私もそのことにうすうす気づいてはいたが、明るそうに振舞って街を案内していた彼が、ここまで爆発的な感情をその奥に抱えていたとは予想していなかった。せいぜい、後ろめたさを感じている程度かと思っていたのだが、マーカスに対する彼の想いは、私の想像を超えて、遥かに強いものであったようだ。
青年は続けてこう言った。
「俺は、マーカスさんを……部隊のみんなを、助けに戻らなくちゃならないんです……」
まったく、どうしたことだろう。マーカスや、このミストという名の青年、そして決死隊に志願したというほかの者たち――ここの遺跡探索隊に属する者は、なぜこんなにも自己犠牲の精神が強いのだろうか? 彼は幸運にも難を逃れて助かったのだ。単純にそれを喜べば良いじゃないか。その上で、自分のために犠牲になった者への感謝の気持ちを少し抱いていれば、それで十分だろう。せっかく助かった命を、みすみすどぶに捨てるなど、愚か者のすることだ。私は、利己的な私や主とは異なる人々の思考に感化されないようにと、心の中で毒づいた。
「キミの話は良くわかった」と、ようやく主が口を開いた。「だが、そうであれば、わたしの口ぞえを得て探索隊に加わろうというのは少し違うのではないかな?」
主がそう言うと、青年は戸惑いと懇願の入り混じった表情を浮かべて顔を上げた。
「ローレンスは私情を抜きにして、任務を達成できる可能性が高い者たちを選出するはずだ。それ以外のことを考慮して、任務を失敗に終わらせることなどあってはならない。違うか?」
その問いに青年は唇を噛んだ。
「見たところ、ここにはキミよりも腕の立つ者がほかにもいそうだ。――だったら、ローレンスにとってキミを探索隊に加える価値はどこにある?」
正論を述べる主に対し、青年は答えに窮した。
手のひらに目を落とし、虚空を握る青年の姿は、はたして自分に何ができるのかを問いかけているように見えた。
「――俺は、一度あの遺跡の中を探索しています。遺跡内部を知る者は俺以外に居ません!」
片手で自分の胸を叩き、青年が答えた。
強い視線を主に向けるが、それは確たる自信を持たぬが故の虚勢であるように見えた。
「それだけか?」
青年の答えにはさした反応も返さず、主は更なる答えを求めた。
続けざまの要求に、青年は一瞬怯んだ。そして、目線を落とした直後、何かに気づいたように顔を上げて答えた。
「俺は、癒しの魔法を使えます! 遺跡探索隊の中でも白魔法に精通している者は限られます!」
「それも評価材料のひとつにはなるかもしれんな……」と、そっけなく言うと、主はさらに続けた。「――ほかには?」
三つ目の答えは、すぐにはでてこなかった。
しばらく悩んだ挙句、青年はようやく、搾り出すような声で「俺は、この任務を果たすためなら命を捨てる覚悟です!」と答えた。
その答えを聞いた主は、冷ややかな視線を青年に向けた。
「それは志願資格の最低条件だ。――ほかには?」
度重なる追撃に、青年は言葉を失ってしまった。だが、一つ目の答えで主を納得させられなかった時点で、あとはいくつ答えを並べても、結果は同じだっただろう。
主の向ける視線に耐えかねた青年が目を泳がせると、主は青年ににじり寄り、逃げずにわたしの言葉を聞け――と、言わんばかりに、その襟倉を捕まえて顔を付き合わせた。
「なあ、ミスト。キミが願うのは、仲間の無事なのか? それとも、自分の後悔を拭い去ることなのか?」
静かな物言いだったが、その言葉は鋭かった。
「ちなみに、ローレンスの願いは、黒い霧を止めることだ。キミの仲間のことは二の次。キミ個人のことなど勘定にも入っていない――。わたしの言いたいことはわかるな?」
逃げることを許されなかった青年の顔は、突きつけられた主の言葉に大きく歪んだ。
二頭の馬に荷馬車を引かせたとして、馬を同じ方向に進ませれば、その力は一頭のときの倍になるが、馬が相反する方へ向かえば、荷馬車は進まないばかりか壊れてしまいかねない。学のない子供でも、直感的に理解できる話だ。しかし、冷静さを欠いた者は、ときにそれすら見失ってしまう。
主は握っていた両手を開いて青年を解放した。そして、ゆっくりと息を吐くと、主にもこんな声が出せるのかと私が驚くほどの穏やかな声で続けた。
「何も探索隊に加わることだけが、マーカスたちを助ける唯一の行為というわけではない。今回、キミが買い物に協力してくれたおかげで、わたしはおおよそ望みどおりの合成素材を手に入れることができた」
主はテーブルの上に置かれた、手のひら程の大きさがある、光沢を放つ鱗を手にとった。
「合成は実に繊細なものでな。素材の良し悪しによって、その成功率が大きく変化してしまうのだ。しかし、これだけ上物の素材が集められれば、成功率はかなり高まるはずだ。それだって、探索隊の任務の成否に直結することだろう?」
そう言って、主が手首を小さく返すと、南側の窓から差し込む光がその鱗に反射して、テーブルの上に綺麗な七色の筋を描く。
「キミが、本当に仲間の無事を願うなら、探索隊へ加わるためにわたしの口ぞえを得るよりも、もっとやるべきことがあるはずだ。キミだからこそ、できることがね」
打ち震える青年は、主の言葉にすぐに答えることはできなかったが、片手で顔を覆い、大きく深呼吸して衝動を押さえ込んだ後、「――チカ様の仰りたいことは……わかりました」と、努めて冷静に言葉を発した。
「取り乱してしまい、たいへん失礼いたしました……。先ほどの条件の話は、忘れてください。ハックの面倒は、きちんとみます。それが、自分にできることの一つだと、貴女が言うなら……。その代わり、必ず、合成を成功させてください……」
その言葉を言い終えるために、青年は何度も呼吸を挟む必要があった。
「了解した」と、主は大きくうなずいた。「安心しろ。わたしは守れない約束はしない。そして、わたしが結んだ約束は、どんなことがあろうとも、必ず果たされてきた」
主はいつになく真摯な目をして、青年の顔を見つめた。
今度は青年もその視線から逃げることはなかった。
青年は本当の意味で主の言葉を理解したのだろうか? 少なくとも私には、合理的な判断ですべてを割り切れるほど、青年は歳を重ねていないように思えた。それでも、葛藤を抱えつつ生きてゆくことで、我々は少しずつ成長してゆくのだ。まだ若い彼には、そのための多くの時間が用意されている。命を賭すのは、もっと年老いてからでも良いだろう。
何にしても、これでこれから数日間の私の身の置き場は決まったわけだ。私は青年の下へ走りよると、その衣服をつたって彼の肩の上まで駆け登った。
《しばらくの間だが、よろしくな、相棒!》
その言葉が理解できたのか、青年は私の方を向いて力なく笑ってみせた。
「では、さっそく合成に取り掛かるとするかな。依頼主が二人になってしまった。これで失敗でもしようものなら、わたしの名も地に落ちてしまう。我が名に懸けて最善を尽くさねばな」
これまで一度として名声など気に留めたこともない主が、わざとらしくそう言った。私にとっては意外なことだが、先ほどからの言動を見る限り、主なりに青年のことを気づかっているらしい。
そんな主に対し、青年は朝方と同じように折り目正しく一礼をすると、静かに部屋を後にした。その手にはカボチャの入った手提げ袋。そして、肩の上に私を乗せて。
部屋の外に出てみれば、がらんどうとした廊下は防寒具なしでは震えが走るほど冷え切っていた。これからますます寒い日が続くことだろう。だが、暖炉の前で悠長に寝ているわけにはいかない。今はやらなければならないことがある。
「俺にできること。俺にしかできないこと……」
氷のように冷たい廊下の上を歩く青年は、そう呟くと足を速めた。